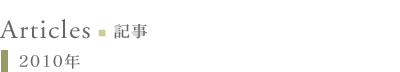
記事:読売新聞2010年11月3日朝刊 |
|
|
 |
||
タクトを振って半世紀。「オーケストラと一緒に育ってきた。受章は協力してくれたみんなのおかげです」と、笑顔を見せる。
裁判官だった父はオペラや協奏曲などクラシック音楽が好きで、家庭には、いつも音楽があふれていた。ピアノを習い始めたのは5歳の頃。抜群の音感で、初めて見た楽譜でも自然に弾けた。そんな素養から指揮者の道を歩むことに。
1962年に桐朋学園短期大学音楽科を卒業。米国留学後、ドイツの作曲家ワーグナーの孫に見いだされたのをきっかけに、ワーグナーのオペラの殿堂バイロイト音楽祭で20年ほど音楽助手を務め、各地の歌劇場で指揮をとってきた。
ワーグナーを得意とする指揮者として知名度も上がり、97年から常任指揮者も務める東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団などを通じ、作品を積極的に日本に紹介してきた。古希を迎えたが、まだ道半ば。「会場が一体となる幸せな瞬間のために、タクトを振りたい」
記事:「音楽現代」2010年10月号 |
|
|
 |
||
準推薦
まず第1番では、その確信に満ちて落ち着き払ったテンポと重厚な響きは、どこかドイツのローカルなオーケストラの演奏を思い起こさせる。飯守は若き日にバイロイト音楽祭をはじめヨーロッパの歌劇場やオーケストラで長く修業を積み重ねた実力派である。東京シティ・フィルの常任として彼の演奏にはしばしば接してきたが、関西フィルは彼の西における手兵である。飯守は10年ほどの年月をかけてこのオーケストラから自分の望む音を作り出すことに成功したわけである。第2番、第4番も同様だが、第3番は多分に室内楽的に扱われている。全体に抑制の効いた地味な演奏ながら、本物のブラームスを聴いた充実感に満たされる。
記事:「レコード芸術」2010年8月号 |
|
|
 |
||
飯守の“ゲルマン魂”〜精緻と迫力の両立
先月号の当欄で小泉和裕&大阪センチュリー交響楽団のブルックナーを紹介したが、今月もまた大阪から、新たな魅力に満ちた録音が発表される。
今年創立40周年の関西フィルハーモニー管弦楽団は、前身であるヴィエール室内合奏団、同フィルハーモニックから1982年に現在の名称になって新発足した。94年に常任になったウリ・マイヤー時代にその演奏は飛躍的に向上したと言われている。現在の常任は01年に就任した飯守泰次郎である。
飯守は、セルとクリーヴランド、オーマンディとフィラデルフィア、ラトルとバーミンガム市響といった、あくまでも指揮者とセットとなったオーケストラの企画とサウンド作りを指向し、長期的なスパンでのオーケストラ運営を目指している。就任後間もなく10年を迎えるこのコンビは、その個性的な音楽作りによって、新たなオーケストラの方向性を打ち出すことに成功している。
ごく若い頃は日本で、60年代終わりからはバイロイトを始めとするドイツの歌劇場で現場の修業を積んだ飯守は、スコアから音楽の劇性を引き出すことに長けている。また「ゲルマン魂」とでも言ってもいい、重厚さと情熱を兼ね備えた音楽を持っている。
そんな彼がついに、手塩にかけた手兵とともにブラームスの交響曲を一挙にセッション録音した。録音されたのは、オーケストラがふだんから演奏会シリーズを開いているいずみホール。キャパシティが821席という広すぎない空間を使って、精密でいながら迫力ある演奏を実現しようとしている。
音楽の情熱と憧憬、その機微に触れる繊細さ
ブラームスの交響曲は、オーケストラにとって試金石となるコアレパートリーである。古典的な構築性を見せつつも情熱的で、重厚でありながらも、その中から精密に組み上げられた音型を聞こえさせなければならない。多面的な要素を持つその作品たちには、これほど演奏機会が多いのにもかかわらず、真の名演に巡り会うことがさほど多いとは言えない。しかし今回、飯守とそのチームはかなりのレベルでその困難さに打ち克った。
まずは第1番をプレーヤーにかけ、再生を始める。しばらくして流れ出てくる音に、ほとんどの聴きてが仰天するだろう。それは最近とんと聴くことのなくなった重みを持った音楽だからだ。ひきずるほどに遅いテンポ、くさびのように打ちつけられるティンパニとコントラバス、その太い土台の上に乗る、重層的に絡み合う旋律線。果たしてこのテンポで、我が日本の演奏家たちは音楽が要求するテンションを維持できるのだろうかとの心配はいつの間にか消え去り、彼らの作りだす音楽に集中している。
そんな序奏から飛び込む主部は、早くはないが推進力の強いテンポ。決して先を急ぐわけではなく、ブラームス独特の息遣いの長さは保たれ、その語尾にはほんの少しのリテヌートがかかる。さらに楽章を聴き進めていくと抒情的なセクションになればとても暖かな歌も、また淋しげな秋風も吹いてきたりする。そして終楽章コーダのすさまじいこと!
全集を通して、常に変転するブラームスの音楽に非常に機敏に、敏感に反応する指揮者とオーケストラ。細部を取り出せば、各楽器の音の細さや奏法の統一、イントネーションや和声的なバランスに一考の余地がある部分もあるが、それよりもブラームスがその精密な楽譜の裏に隠した暗い情熱や憧れ、感情の強い発露の実現に集中しているようだ。これほど個性的で表現的で、日本人なればこその繊細な音色感までも突き詰めようとしたこの演奏は、その突き詰め方の徹底によって逆に普遍性を得たと言えるかもしれない。
記事紹介 |
|
|
 |
||
飯守&シティ・フィルが展開中の「ベートーヴェン交響曲全曲シリーズ」――イーゴリ・マルケヴィッチによる校訂版使用――の、今夜は第3回。「第1番」と「第3番 英雄」が取り上げられた。
それに先立ち、「レオノーレ」序曲第3番も(これはマルケヴィチ版ではない)。
このシリーズ、注目はしていたのだが、漸く今回初めて聴くことができた。
私は、マルケヴィチの校訂楽譜そのものを見ていない。それゆえ詳細を知る機会を得ないし、どこまでが「マルケヴィチ」で、どこからが「飯守」なのかも――如何なる演奏においても、指揮者自身の「解釈」は必ず混じって来るからである――確定的なことは解らない。(註1)
だが、とりあえず今日の演奏を聴いて確認できたのは、スタッカートや錘点(楔)の区別が非常に明確であり、全曲が著しくリズム性に富み、尖ったメリハリのある演奏になっていることだ。
随所に付された明快なアクセントは小気味よいほど強く、音楽をきわめて躍動的なものにしている。それを念頭に聴いているだけでも、興味津々、スリルを覚えるほどである。
もっとも、その特徴にだけ関して言えば、新ペータース版やベーレンライター版などの楽譜が登場した時に、私たちはすでにそれらを体験済みだ。
むしろ注目すべきは、それ以前の時期――1983年に他界したマルケヴィチが、いち早くそれらを含む問題点を考察したスコアを作っていた、ということであろう。
スタッカート以外にも、おそらくもっと多くの興味深い問題が提起されていることだろう。
第4楽章冒頭、第1主題がまずピチカートで登場したあと、木管が合いの手を入れながら繰り返される個所(第20〜27小節)で、弦はピチカートでなく、アルコで演奏された。意外だったが、しかしこれは以前にも、誰かの指揮で聴いたような気がする。
ただ、第1楽章最後の頂点でのトランペットは、主題を最後まで吹き切るという「伝統的な慣習」が相変わらず採られていたが、これは「マルケヴィチ」なのか、「飯守」なのか?(註1)
飯守の情熱的な指揮のもと、シティ・フィルも見事な演奏をしていた。特にオーボエの1番奏者は素晴らしい。すこぶる聴き応えのある演奏であった。
私個人の好みからすれば、前夜のプレートル&ウィーン・フィルによるトラディショナルな「英雄」よりも、今日のこの角張った「英雄」の方が興味深い。
終演後、飯守泰次郎氏の叙勲(旭日小綬章)祝賀パーティが、ホールの2階ホワイエで行なわれた。
(註1)後日、有名な個人旅行エージェントの方から、出版譜をお借りすることができた。面白い校訂が山ほどある。「英雄」第1楽章最後の「トランペットの件」はマルケさんの校訂ではなく、飯守氏の考えであることが判明。

(c) Taijiro Iimori All Rights Reserved.